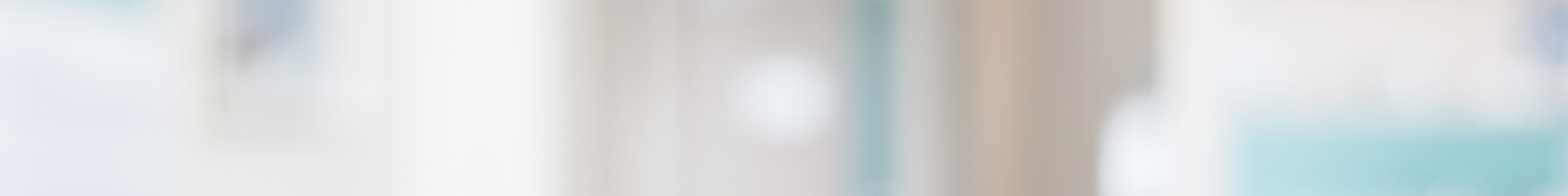
一般内科・頭痛外来
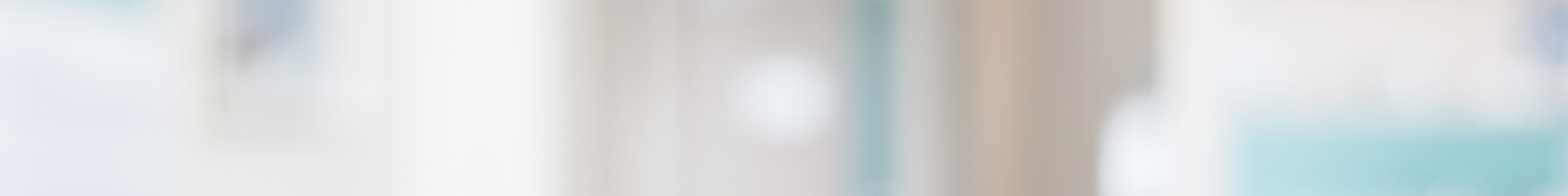
一般内科・頭痛外来

一般内科では、日常生活の中で比較的遭遇しやすい急性症状や慢性疾患の継続的な治療とコントロールを行っています。以下に内科でよく見られる症状を挙げています。複数の症状が出ていて「何科を受診したらよいかわからない」といった場合など、お悩みの際はお気軽にご相談ください。
このような症状と疾患の方はご相談ください
かぜは正式には「かぜ症候群」といって、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰などを主症状とする上気道(鼻やのど)の急性炎症の総称です。発熱、咽頭痛、全身倦怠感、食欲低下などを伴う場合がありますが、発熱はあっても微熱程度で、頭痛や全身倦怠感などの全身症状も軽いという特徴があります。
原因微生物の80~90%はウイルスが占めており、粘膜から感染して炎症を起こします。きちんと治さないとその後、気管支炎や肺炎に進行する場合もありますので、治ったと思って無理をせず、完治するまで来院されることをお勧めします。熱を含めた症状の経過をしっかり観察することが大切です。
インフルエンザウイルスによる急性熱性感染症で、A、B、の2型があり、通常、寒い季節に流行します。感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、38℃以上の突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの症状がこれらに続き、およそ1週間で軽快します。主な合併症としては肺炎、脳症が挙げられます。通常のかぜ症候群とは異なり急激に発症し、全身症状が強いことが特徴です。
季節性インフルエンザはいったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。
胃腸炎のほとんどはウイルス感染(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)で、一部に細菌性(カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌など)が見られます。ウイルスが付着した料理を食べたり、手指についたウイルスが口に触れたりすることで感染し、冬場、幼稚園や小学校などで集団発生することも少なくありません。
症状は下痢、腹痛、嘔吐、発熱が多く、治療は脱水を予防し、症状に合わせた内服薬を服用します。細菌性が疑われる場合には抗生物質を使用することもあります。脱水予防には、自宅で出来る経口補水療法が効果的です。
じんましんは皮膚の一部が突然くっきりと赤く盛り上がり(膨疹)、しばらくすると跡形もなくかゆみと皮疹が消えるという特徴があります。たいていかゆみを伴いますが、チクチクとした感じや焼けるような感じになることもあります。発症して6週間以内を「急性じんましん」、それ以上経過した場合を「慢性じんましん」と呼びます。
じんましんの治療は、まず原因や悪化因子を探して、それらを取り除く、または避けるようにすることです。アレルギーが原因であれば、原因アレルゲンや刺激を回避します。仕事や勉強などのストレスや不規則な生活を避けることも重要です。薬物治療は、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などの飲み薬が中心となります。
扁桃炎は、のどの奥の左右両側にある扁桃が、細菌などの感染により炎症を起こす病気です。扁桃が赤く腫れ、白い膿を持つこともあります。扁桃炎の症状は、のどの痛み(とくにつばを飲み込むときの強い痛み)、発熱、あごの下や頚部のリンパ節の腫れなどですが、耳や側頭部に痛みが放散することもあります。扁桃炎の治療は、軽い場合はうがい薬、トローチの使用などで改善しますが、炎症が強い場合は、抗生物質、消炎鎮痛剤、解熱剤などを服用する必要があります。
日頃はよくうがいをして、不摂生をしないことが大切です。痛みがある場合は、入浴、飲酒、喫煙は避けましょう。
日常的に頭痛に悩まされ、つらくても「頭痛くらいで…」という思いから、医療機関を受診せず、市販薬を服薬して対処されている方も少なくありません。頭痛外来は、そのようなつらい頭痛に悩まれている方々のための窓口であり、様々な頭痛の症状に対して、医学的に診察、検査、診断、薬の処方を行います。
片頭痛の名称は頭の片側が痛むことに由来しますが、両側の頭痛を経験する方もいます。女性に多い傾向があります。
頭痛の前に、キラキラと何かが見える、ギザギザの光が見える、といった視覚性の「前兆」があるものとないものがあり、前兆は多くの場合、60分以内に終わり、続いて頭痛が始まります。頭痛はズキンズキンと脈打つように痛み、吐き気や嘔吐・眠気を伴うこともあります。光や音、匂いに敏感になることもあります。片頭痛の発作は通常4~72時間程度で、症状が消えると普段と変わりなく過ごすことができます。
片頭痛は完全に解明されていないものの、疲労やホルモンバランスの変化、光や音の強い刺激などによって、三叉神経という神経から炎症物質(CGRP:痛みの直接の原因とされているタンパク質)が放出され、硬膜(脳の表面の膜)に炎症と血管拡張が生じて起こると考えられています。
片頭痛の治療は、頭痛発作を早く鎮めるための急性期治療と、頭痛がない日も毎日お薬を飲んで、頭痛発作を起こりにくくする予防療法があります。
緊張型頭痛は頭痛の中で最も頻度が高く、後頭部、こめかみ、ひたいを中心に頭重感や圧迫感、または締めつけられるような痛みがジワジワと発生し、しばらく続きます。眼の奥が痛くなることもあります。
筋肉の緊張(血行障害)、あるいは精神的・肉体的ストレス、疲労、自律神経の乱れなどによって起こります。長時間、パソコンや車の運転などで前屈みやうつむきの姿勢が続くと、頭や首、肩の筋肉に負荷がかかり、血流が悪くなって頭痛が起こりやすくなります。
群発頭痛は、片側の目の奥がえぐられるような強烈な痛みが起こります。一定期間に集中して起こるため「群発」という名称がついています。年に1~2回程度発症し、群発期には1回につき数十分から2時間程度の激しい痛みが生じ、1~2カ月にわたって続きます。1日に何度も起こすこともあります。比較的稀な疾患で、男性に多く発症する傾向があります。
二次性頭痛は病気が原因で起こる頭痛です。見逃すと危険性が高い病気には、くも膜下出血、脳腫瘍、脳梗塞、脳出血などがあります。
頭痛に加え、以下のような症状が伴う場合には、脳の病気が隠れている可能性があります。速やかな受診が必要です。
TOP